生殖補助医療胚培養分野(修士課程)
保健医療学専攻
生殖補助医療胚培養分野
生殖補助医療胚培養分野オンラインオープンキャンパス
- 開催日時
- 7月19日(土)13:00~14:00
- 内容
- 13:00~13:10 当分野の紹介
13:10~14:00 質疑応答
※当日はMicrosoft Teamsを使用して行います。接続リンクは開催が近くなりましたらこちらに掲載します。
※キャンセルの場合は、大学院入試事務室までメールにてご連絡ください。
大学院入試事務室 daigakuin-nyushi@iuhw.ac.jp
■個別相談は随時、受付しております。下記の担当教員宛にメールでご連絡ください。
猪鼻達仁 講師 (山王病院 リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター 培養室)
<連絡先> E-mail:ihana-tatsuji-bf@ihwg.jp
(メールを送る場合は、@マークを半角文字で入力しなおしてください。)
胚培養士(エンブリオロジスト)は学会の努力もあり資格制度が定着しつつありましたが、教育機関において胚培養士の養成に特化した正式なコースはありませんでした。胚培養士の技能が治療成績を左右すると言っても過言ではない現在の生殖医療において、十分な知識と技術を兼ね備えた胚培養士を養成することは急務でありました。そのため生殖医療分野において多くの実績を有する山王病院(本学臨床医学研究センター)などと協力し、2005年に日本で初めて胚培養士養成のための大学院修士課程を開設しました。現在までに約100名の入学者を数え、現職胚培養士のキャリアアップ、胚培養士への就職を目指す方に対し生殖医療に関する集学的、学際的な知識およびラボワークに必要とされる技術をバランスよく習得していただくことを支援しています。また単なる技術だけでなく、科学的裏付けを持つ思考により、さまざまな状況に対応できる「考える胚培養士」を養成することを目指しています。当分野では社会人を含めた様々なライフスタイルの方々に就学していただけるよう必須科目(講義のみ)および一部の選択科目はVOD(ビデオ・オン・デマンド)に対応しています。そのため都合により受講できなかった場合でもWeb上で視聴し、課題を提出することで単位認定につなげることができます(視聴期間には期限があります)。なお既に胚培養士として勤務しており、当学と勤務先が委託契約を締結できた場合、委託実習という形態を選択することもできます。そのため全ての実習時間を委託実習先のみで実施することもできます(詳細は担当者までお問い合わせください)。
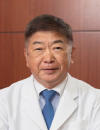
東京大学卒、医学博士、米国国立衛生研究所(NIH)留学、東京大学大学院教授を経て、平成20年より本大学院教授。山王病院名誉病院長。元東宮職御用掛。
日本産科婦人科内視鏡学会監事、日本受精着床学会副理事長、日本母性衛生学会理事、日本内視鏡外科学会名誉会員、日本生殖医学会功労会員、元アジアパシフィック産婦人科内視鏡学会理事長、中日友好病院(北京)名誉教授。
日本産科婦人科学会専門医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医、日本生殖医学会生殖医療専門医、日本内視鏡外科学会技術認定医、母体保護法指定医師 。
修業年限: 2年
取得できる学位・資格:修士(生殖補助医療学)
<分野の教育内容等に関するご相談窓口>
猪鼻達仁 講師 (山王病院 リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター 培養室)
<連絡先> E-mail:ihana-tatsuji-bf@ihwg.jp
(メールを送る場合は、@マークを半角文字で入力しなおしてください。)
生殖補助医療胚培養領域
上記の分野についての説明に沿った内容で、講義・演習・研究指導を展開し、各学生の研究テーマに応じて修士論文及び研究指導を行う。
担当教員 ※太字は研究指導教員
- 氏名
- 主な研究指導内容
専門科目
- 生殖補助医療胚培養基礎系講義[修士] I(配偶子形成と受精)・II(胚発生と培養環境)
- 生殖補助医療胚培養臨床系講義[修士] I(生殖補助医療概説)・II(不妊症学)
- 生殖補助医療胚培養実習[修士] I(精子処理)・II(卵子・胚処理)
- 生殖補助医療胚培養課題研究指導
お問い合わせ・連絡先
国際医療福祉大学大学院
東京赤坂キャンパス事務局
- 〒107-8402
東京都港区赤坂4-1-26 - TEL.03-5574-3900(代表)
FAX.03-5574-3901 - E-mail:
tokyo.s.c@ihwg.jp
(メールを送る場合は、@マークを半角文字で入力しなおしてください。)