医療福祉ジャーナリズム分野(修士課程)
医療福祉経営専攻
医療福祉ジャーナリズム分野
■7/20(日)にオンライン説明会を開催します。こちら からお申込みください。
■大学院生による紹介動画を公開しています。以下からご覧ください。
大学院生による分野紹介
少子高齢化社会が進む中、医療・福祉を専門とするジャーナリストの重要性が指摘されていますが、これまで全国の大学では養成の場はありませんでした。医療福祉関連施設でも広報の重要性が高まり、そのための必要な知識・技術は、医療福祉ジャーナリズムと共通のものが数多くあります。こうした社会的要請にこたえて、本大学院では2005年、医療福祉ジャーナリズムの知識・技術を深めるコースを新設しました。全国でも例のない「医療福祉ジャーナリズム分野」です。2024年度までに、修士・博士の取得者は、70人(修士64人、博士6人)に達し、各界の一線で活躍しています。
本分野では、新聞社で経験を積んだ、著名なジャーナリストが、教授として教鞭をとっています。さらに、各キャンパスでは、医療福祉の専門大学ならではの医療福祉関連の基礎的な講義が広い分野で行われ、他分野の教員、学生を通じて、生きた医療や福祉の知識を学ぶこともできます。ジャーナリズム分野の院生は、自分の興味や関心に応じて、研究テーマを選ぶことができます。講義や演習を通じて、課題研究の方法を学び、指導教官から研究指導を受け、修士や博士の論文に取り組んでいます。
修士・博士作品のテーマはまことに多彩です。医療事故の被害者による「医療に安全文化を」の提案、縛らない医療の先駆看護師による「さらばオムツ」、鹿児島をモデルケースに考察した「地域包括ケアにおける保健師の役割」、看護師のがん体験と生き方の考察、ケアマネジャーの「美しく生き生きと老いること」、薬の文化論—など。博士論文も、スウェーデンの認知症ケアをテーマとした「ケアの概念としてのオムソーリ」など6編を数えます。
我が国を襲ったコロナ禍は、少子高齢化の流れを加速させ、出生数は過去最低を記録し続けています。高額療養費問題など、増える社会保障費をだれが負担するのか。世界に誇れる国民皆保険制度が問われています。志をもち、何か世のため人のために役に立ちたいと思っているあなた。一緒に学びませんか。

名古屋大学教育学部卒、読売新聞東京本社医療情報部長、生活情報部長などを経て、2007年4月から本学教授。同大医療福祉・マネジメント学科長、常務理事、医療福祉学部長などを歴任。
修業年限: 2年
取得できる学位・資格: 修士(医療福祉ジャーナリズム学)
分野の教育内容等に関するご相談は分野責任者へ
医療福祉ジャーナリズム領域
伝えるために必要な基礎知識から手法までを幅広く学び、ジャーナリズム、マスメディアの世界で活躍できる実力を
際医療福祉大学大学院 医療福祉ジャーナリズム分野は、医療福祉ジャーナリズムについて研究し、修士、博士号を取得するだけでなく、書籍などの「作品」をつくりあげることもめざしています。新聞・雑誌・TV・医療・福祉の世界で実績ある多彩な教授、ゲスト講師による充実した講義、ゼミ、そして作品づくりのバックアップを受けられます。加えて、医療福祉経営学、医療福祉政策学、医療福祉心理学、国際感染症学、看護学、理学療法学、作業療法学、聴覚障害学、視機能療法学など他の分野の教授陣の講義を受けて知識の幅を広げることもできます。作品は、出版されTV番組として放送されるなど、さまざまな形で世の中に発信されています。
2020年度は、ケアマネジャー、保健師、社会福祉士の3人が、期せずして認知症をテーマに取り上げ、「地域で暮らすことが困難」と判断され理由、「希望をもって日常生活を過ごせる社会の実現」、「当事者音の主権回復に挑んだ3人の看護師」をテーマに論文を執筆、その後、加筆修正し、一冊の本にまとめ上げています。
ジャーナリズム水先案内人
丸木 一成 教授
読売新聞の看板シリーズ「医療ルネサンス」の"育ての父"。東京本社編集局医療情報部長もつとめる。編著に『医療ルネサンス』『医療の質向上への革新』etc.
埴岡 健一 教授
日経ビジネス副編集長、日本骨髄バンク事務局長、日本医療政策機構理事、東京大学公共政策大学院医療政策教育・研究ユニット特任教授など。
大熊 由紀子 教授
"日本の福祉を変えた本"と呼ばれる『「寝たきり老人」のいる国いない国』などの著者。朝日新聞論説委員、大阪大学大学院教授を歴任。国内外の現場や行政官に広い人脈をもつ。
染谷 一 客員教授
読売新聞社取材記者職(編集局医療情報部、文化部など)、調査研究本部主任研究員、医療ネットワーク事務局専門委員等を歴任。

3年かけて修士号を取得した仲良し3人組の晴れ姿(2023年3月・学位授与式)

遠隔参加も可能な修士1年のゼミ風景

全盲の弁護士をゲストに迎えてのゼミ、普段は海外からのZoom参加者も入って記念写真

感染防止に注意を払い対面での授業、ビデオでも受講できます

ゲスト講師、患者と家族と医療をつなぐNPO法人架け橋の豊田郁子さん(奥中央)を囲んでの「放課後」懇親会
修了生の主な論文
2024年度 修士論文
中烏 薫さん(修士)
都道府県感染症予防計画の改善点の提言 ~ロジックモテルを活用した整合性評価による検討~
GOU FENGさん(修士)
在留外国人が抱える医療に関する困りごとへの支援策の考察 ~東京23区の行政機関を対象に~
佐藤 柊さん(修士)
学校における「ネットいじめ」の防止に向けて ~先進的に取り組む自治体の現状と課題を考察する~
金子 恵妙さん(修士)
的障害のある人の子育てをめぐる「きれいこと」と「人権」の間 ~先進的取り組みから解決の方向を考察する~
河野 礼子さん(修士)
「本人の希望」と「家族・支援者の困りごと」の乖離を「見える化」する試み ~本人の「できる」を引き出す支援方法を見いだすためのF-SOAIPバージョンアップの提案~
2023年度 修士論文
高橋 祐美子さん(修士)
コロナ禍において臨床試験・臨床研究はどう報道されたか?~新聞記事の内容分析からの考察
松田 清人さん(修士)
精神病床を有する病院に入院している認知症のある人の身体拘束を減少させる ~地域差の要因を明らかにし考察する~
速水 沙恵さん(修士)
母子健康手帳を使用する際に外国籍妊産婦が抱える課題の考察 ~首都圏の事例を用いて~
2022年度 修士論文
八木 亜紀子さん(博士)
テキストマイニングによるソーシャルワーク記録の考察~医療ソーシャルワーカーを対象にして~
北澤 浩美さん(修士)
歯科衛生士が地域での多職種連携を 実践するポイント ~住民の口腔の健康を維持向上するために~
吉田 和佳子さん(修士)
不適切な薬剤処方の改善策とその普及 ~医師と薬剤師の挑戦から学ぶ~
青木 隆子さん(修士)
離島遠隔地の持続可能な"お産"の考察 〜ローカルメディアが探る可能性〜
大沢 理奈さん(修士)
次期へき地医療計画のあるべき姿~ロジックモデル(論理構成図)を作成し関係者の意見を集約する~
山口 久美さん(修士)
知的/発達障害がある人の真の意思に向き合う~「私たちぬきに私たちのことを決めないで」の原点に立ち返るため
金沢 みぎわさん(修士)
聴覚障害者と共にある聴者の葛藤 〜他の障害および双⽅のインタビューによる 関係性の考察〜
2021年度 修士・博士論文
岩田 真弓さん(博士)

博論のタイトルは「ナラティブからみるオーストラリアで働く日本人看護師の経験~柔軟な文化や組織・教育の視点を探る」。オーストラリアの看護師経験17年を生かし、文化背景の異なる患者の看護に必要なことを、国際化の進む日本の現場への提言
伊藤 かおるさん(修士)

「闘病記を書く意味~16年後に書きながら考える」。2004年、当時5歳の次男を悪性脳腫瘍で亡くした。当時の日記をもとに、闘病記を書くだけでなく、16年後に闘病記を書く意味を、悲しみと向き合いながら考察した、労作だ。病児や家族の心理的苦痛を軽減するための素材の提供との思いから始めた考察は、体験者ならでは指摘も多く、チームで支える提案もしている。
2020年度 修士論文
永野 富美子さん(修士)
認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会の実現を目指す挑戦

平岩 千代子さん(修士)
認知症当事者の主権回復院に挑んだ3人の看護師
修士論文をもとに、「"認知症と拘束"尊厳回復に挑むナースたち」を2021年10月、出版
藤村 忍さん(修士)
認知症の人が「地域で暮らすことが困難」と判断される要因とその構造的課題
認知症というテーマが共通したことから、指導教官の大熊由紀子教授を交えた「課題研究を書き終えたいま~認知症のある人をめぐって~」の座談会を巻頭に、修士作品に発表スライドを加えた「課題研究作品集」を2021年3月に出版した。
2019年度 修士論文
相澤 万紀さん(修士)
慢性呼吸器疾患の栄養ケアのあるべき姿を考える~患者に"食"が寄り添うために~
浅野 泰世さん(修士)
患者が「人を対象とする医学研究」に参加する意味の考察~DIPEx-Japan「臨床試験・治験の語り」テキストデータの分析から~
清田 政孝さん(修士)
がん患者に理解しやすい施設別情報提供の仕方~満足してがん治療を受けるために~
鈴木 隆子さん(修士)
車いすに乗った谷口明広先生ものがたり~自立生活に向けての奇跡とメッセージ~
59歳で急逝した「障害福祉の師匠」の伝記を書くために入学、2023年5月、論文を加筆し「障害があるからおもろかった 車いすに乗った谷口明広さん物語」を出版
田原 浩子さん(修士)
住民が主役の地域づくり政策に関わる行政側の現状と課題~生活支援体制整備事業の「協議体」に着目して~
村田 優美さん(修士)
美しくいきいきと老いること~アピアランスケアに深さと広がりを~
修士論文をもとに、『美しい歳のとり方は「介護の現場」が教えてくれた』を2022年3月出版。より自分らしく生きるための41のマストルールを説く。
これまで提出された修士、博士論文のテーマは多彩で、「自宅の安らかな死を制度の提案」、「医療事故が起きないためのシステムを日本で構築するために」、「尊厳ある認知症ケアの具体的な方策」、「日本の現場とデンマークの地域包括ケアを比較して提言する」など、それぞれ、自身の現場で実践しつつ模索を続けています。
2年連続で各4名がデンマークとスウェーデンに滞在しての調査研究の機会をもちました。ドイツを拠点にヨーロッパ諸国を取材した院生もおり、互いの特技を持ちより、実に仲良く切磋琢磨しつつあります。
2018年度 修士・博士論文
西村 多寿子さん(博士)
「日本の臨床研究の質向上に向けてメディアの果たす役割」~研究不正の報道は臨床研究のルールづくりに影響を与えたのか~
井手 公正さん(修士)
日本とデンマーク、両国を経験した留学生の障害者観の変化 ~障害当事者の視点で原因を分析する~
田中 知世子さん(修士)
「要介護状態になったとき自宅で生活を継続するための条件」~100年人生を自分らしく生きるために~
月﨑時央さん(修士)
精神病薬を断薬して回復した人々の物語ー当事者の語りから考察する薬の適正使用ー
修士論文をもとに「新版 ゆっくり減薬のトリセツ」を、2022年5月、出版
修士論文がもとで生まれた書籍




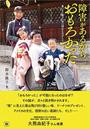
担当教員 ※太字は研究指導教員
- 氏名
- 主な研究指導内容
専門科目
- 医療福祉ジャーナリズム概論
- 医療福祉ジャーナリズム特論
- 医療福祉ジャーナリズム演習 I(文献講読)・II(論文クリティーク)
- 医療福祉ジャーナリズム課題研究指導 I(研究計画作成)・II(論文作成)
お問い合わせ・連絡先
国際医療福祉大学大学院
東京赤坂キャンパス事務局
- 〒107-8402
東京都港区赤坂4-1-26 - TEL.03-5574-3900(代表)
FAX.03-5574-3901 - E-mail:
tokyo.s.c@ihwg.jp(大学院全般について)
daigakuin-nyushi@iuhw.ac.jp(入試や事前相談について)
(メールを送る場合は、@マークを半角文字で入力しなおしてください。)