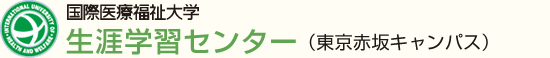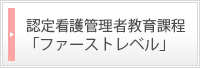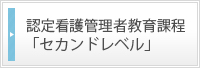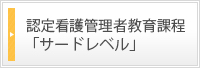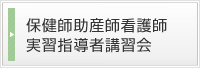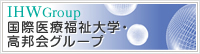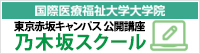当センターにおける認定看護管理者教育課程は、平成18年(2006年)にファーストレベルを開講、平成19年(2007年)にセカンドレベル平成21年(2009年)にはサードレベルを開講しました。
この間当センターから2,500余名が修了し、各職場で活躍しています。
また、2013年度から開催のフォローアップ研修は、受講者、修了者にとって更なる研鑽の機会となります。2021年度からは3課程合同にて開催、学びと交流の有意義な研修となっております。
以下に当センターでの受講を終えられた方の感想をご紹介いたします。
- 認定看護管理者
教育課程を受講して - 認定看護管理者
審査に合格して
認定看護管理者教育課程 ファーストレベルを受講して
NEW2025年度(1回目)日本医科大学付属病院 山根 幸子
私は、一般病棟で主任看護師として看護師長を補佐し、病棟スタッフの育成に関わっています。時間外勤務の削減や業務改善に取り組んできましたが、思うように成果が出せず、どう解決していくか悩んでいました。そんな時に師長から受講を勧められ、管理的な視点や問題解決技法を学び、自部署の課題解決につなげたいと思い受講を決めました。
講義では、業務改善を進めるためには、幅広い知識や多角的な視点が必要であることに気づかされました。また、講師から繰り返し「患者を主語に考えること」の大切さを教わり、これまで看護師中心の視点になっていた自分に気づきました。今後は「患者を主語」に課題を捉え、看護実践に結び付けていきたいと思います。
統合演習では、グループワークで意見を出し合いながら、「あるべき姿」や課題の適切さについて検討しました。多様な意見を聞くことで、自部署の問題をより深く掘り下げることができ、他の受講生の課題も自部署に置き換えて考えることで、新しい視点を得ることができました。
国際医療福祉大学のファーストレベル講習は、週末型であり、最初は仕事との両立ができるのか不安はありましたが、受講生同士で励まし合いながら、一緒に乗り越えることができました。また、仕事と講義の両立だからこそ、何か問題にぶつかったときに講義で学んだことをすぐに実践で活かすこともできました。他の受講生とも自部署で起こっている問題について共有しながら、解決方法を一緒に考え、アドバイスをもらうことができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。
今後も学んだことを活かしながら、常に「患者を主語」に問題を考え、自部署の問題が解決していけるように自職位でできることを踏まえ看護管理を行っていきたいと思います。
2024年度順天堂大学医学部附属静岡病院 飯田 沙耶香
私は、一般病棟の主任として看護管理に携わっています。日々、師長と共に看護管理を行う中で、多角的な視点を持ち管理業務を行うこと、人材育成や看護チームのマネジメントなどについて学びを深めたいと本研修に興味をもちました。さらに、自部署で病院機能評価受審と部署移転という重要な行事を通して、ヒト・モノ・カネ・情報の資源活用やリーダーシップを発揮することが課題であると実感しました。そこで、組織管理能力と人材管理能力の向上を図りたいと本研修の受講を希望しました。また、研修の開催方法がオンライン主体の週末型研修であることも、地方に住んでおり未就学児がいる私にとっては、受講したいという意欲を高めたきっかけとなりました。
今までも目の前にある問題は真の問題なのか、と考え対策を立ててきたつもりでしたが、思うようにいかず難渋することが多々ありました。各領域の講義やグループワークを通して、問題解決技法を丁寧に学べび、上手くいかなかった要因として自分たち医療者を主語にして考えていたことに気づくことができました。担当の先生方から幾度となく『あるべき姿は患者を主語に考えること』とご教授いただいたことで、問題解決技法の理解を深めることができ、今後も大切にしていきたい学びとなりました。課題レポートの作成は、短期間で仕上げることはとても大変でしたが、自部署の現状から患者のあるべき姿、課題を文字に起こして考えることで、思考の整理ができました。各領域のレポートは先生方からのご助言をいただいたため、ブラッシュアップさせ課題解決に活かしていきたいと思います。
研修中に辛くなったこともありましたが、勤務地や病院の機能、役職が様々な多くの受講者と、グループワークや演習を通してテーマ以外のことも情報交換し語り合う機会があり、多くの刺激を受け、楽しく研修を受講することができました。
本件種での学びを、部署運営に活かし、師長・スタッフと共に患者にとっての最善を考え、今後も課題に取り組んで成長していきたいと思います。
2023年度(2回目)訪問看護ステーションわっか 浜屋 健司
私は、訪問看護ステーション所長として、医療・介護・福祉に関わる領域の中で質管理や人材育成、地域社会への貢献ができるよう、看護管理について学びを深めたいと考え受講を希望しました。
これまで問題に直面した場合、すぐに対策を考え対応をしていましたが、真の問題は何か、利用者のあるべき姿から問題を掘り下げ分析する問題解決手法を深く学ぶことができました。
各領域の講義では、自部署で起きている問題について利用者を中心に考えることができ、問題の整理や自職位が取り組むべき課題を明確にすることができました。
また、週末型の講義であるため、勤務を継続しながら受講することができました。受講の際にできた仲間に週末会えることが楽しみで、あっという間の20日間となりました。
課題レポートへの取り組みが大変なこともありましたが、講義以外でも先生方のサポートが受けられ、安心して受講することができました。レポート作成では、文章の書き方も学べるので、受講前とは見違えるほどレポート作成の内容が変化していることに気が付きました。
訪問看護以外に病院や施設で活躍される他の受講者の方と学びを共有でき、視点を大きく広げることができました。それぞれの立場で情報共有をし、実践レベルで連携をする際に、病院と訪問看護の連携のあり方や、病院や施設、在宅の医療体制を理解して対応することなど相手の立場を理解し、医療・介護領域における連携を深めることができました。
講義の中でグループワークが多くあり、活躍するフィールドは異なりますが、多くの仲間と出会え、お互いの看護観について語り合えたことも楽しく受講できた理由の一つです。
演習を通して、自部署の現状が理解でき、訪問看護での役割を果たすために自職位として何をすべきなのか学ぶことができました。
この演習で学んだ問題解決手法を活用して考え、実践する能力を高めていきたいと思っています。
認定看護管理者教育課程 セカンドレベルを受講して
NEW2025年度東京都立病院機構 東京都立大塚病院 原田貴和
私はこれまで新生児・小児看護領域の経験が長く、成人病棟に配属になった際に日本の医療政策への知識不足を実感しました。政策動向を踏まえた看護管理の在り方を学びたいと考え、セカンドレベル研修を受講しました。国際医療福祉大学のコースは長期間にわたる研修ではありますが、週末型であるため、教科目レポートの中で検討した実践計画に着手しながら受講を進めることができることが最大のメリットだと思います。
特に印象深かった講義は、ヘルスケアシステム論です。日々の管理業務の中で、情報収集は文字化された公開情報に頼りがちになっていました。しかし、医療政策の方向性を理解するためには、資料に埋め込まれた情報を深く読み解く必要性があることを学びました。管理者として、これからの看護に求められることは何かを正しく把握することが、人材育成や資源管理を進めるうえで不可欠であると強く感じました。そして、教科目レポート作成では、「相手がどう読んでくれるか」という視点で表現することの重要性を学びました。これは管理者として必要な交渉力にも役立つものであり、自分が伝えようとする内容が、相手の意思決定や行動につながるかを考えるトレーニングになったと思います。
統合演習でのグループワークでは、感覚で捉えていた事象の背景にある現状を可視化し、自分やスタッフが望むことではなく、患者にとっての「あるべき姿」は何かを問い続けました。異なる施設のメンバーや講師の先生から多様な意見をいただくことで、自身の理解の枠組みを取り払い考察する機会になりました。さらに、グループメンバーそれぞれの所属組織の現状把握から組織分析、改善計画立案までのプロセスを共有できたことは、異なる現場での管理業務の疑似体験となり、自身の限られた経験を補う学びとなりました。
研修修了時には、ご支援いただいた国際医療福祉大学の先生方が「ここからがスタート」と背中を押してくださいました。思考を止めることなく、本研修で得た学びを、今後の看護管理の実践に活かしていきたいと思います。
2024年度神奈川県立循環器呼吸器病センター 関口 秀美
私は、認定看護師として組織横断的に活動する中で、データを活用し看護を可視化することや、多職種協働の仕組みづくりなど、実践を通して管理的視点を学んできました。その後看護科長となり、自部署の課題に向き合う中で、経験に頼った物事の判断や、地域社会に目を向けた上で自部署の課題を捉えられていないことが分かりました。そこで、系統的に看護管理を学び、自身の課題に取り組みたいと考え、セカンドレベルを受講しました。
国際医療福祉大学での受講の決め手は、オンライン授業が主であること、ファーストからサードまで段階的に受講できること、そして何より講師の方が充実していることでした。
実際に受講してみると、管理業務をしながら週末に学ぶ受講者が、一つ一つの課題にしっかり向き合えるようスケジュールが工夫されていました。そして、教科目ごとに徹底的に問題解決思考を学び、情報化社会の中で、データと理論で説得し組織変革する力を養うカリキュラム構造となっていました。また、授業のたびにグループワークを行い、他施設の受講者と活発に意見交換する中で、外部から見た自施設のあり様や、自身の強み弱みもこれまで以上に明確になりました。
本研修で特に学びとなったのは、地域・医療のニーズから自部署の問題として一貫した問題解決思考で対策を導き出すプロセスと、自施設内の状況だけではなく他院や地域の現状、今後の動向などから変化を予測した対策を講じる視点です。
統合演習では様々な経験を持つグループの仲間と、多角的な視点でそれぞれの所属部署の現状分析を行い、グループダイナミクスの効果を実感しながら、看護管理のプロセスを可視化していきました。そして、実践しながら学ぶ環境を活かし、統合演習で導き出した看護管理改善計画をタイムリーに実行しました。取り組んだテーマはこれまでも感覚的に問題と感じていたことではありましたが、丁寧に根拠を積み重ね、そのプロセスを可視化することで、人を巻き込みチームを動かす影響力となることを実感しました。
本研修での学びを活かし、さらに看護サービス向上につなげられるよう、あきらめずに継続して取り組んでいきたいと考えています。
2023年度千葉労災病院 杉野 正
私は国際医療福祉大学でファーストレベルを受講し、引き続き同学のセカンドレベルを受講しました。受講当時の私は大学病院勤務を経て、都内の在宅医療(訪問診療・訪問看護)を専門とする医療法人に勤めていました。法人事業の拡大に伴って管理者になりましたが、看護管理を系 統的に学んだ経験はありませんでした。一方で都市部における在宅医療ニーズは年々増加し、持続可能なサービス提供体制を構築することが組織の課題でした。このような問題意識のもと、認定看護管理者教育課程での学習を通して、自己実現していくキャリアプランを描きました。二 度の受講に際し、法人や同僚の協力を得ることができたのも幸いでした。 講義は約4ヶ月の期間、週末を中心にオンライン形式で行われました。講義資料データの受取り、グループワーク、課題レポート提出、ほぼ全てがオンラインで完結します。また、オンラインで のグループプレゼンテーションを通して、ファイル共同編集などのITスキルを習得する機会も得ら れます。近年定着しつつあるこの学習スタイルは、働きながら学ぶ上で、非常に時間効率が良かったと思います。
セカンドレベルでは、教科目毎に比較的多くの時間をグループワークに費やしました。異なる組織・職位の受講者と、対等な関係でディスカッションできた事は貴重な体験でした。学習内容を実践にフィードバックする点で、目的意識の高い受講生が多い印象を受けました。例えば私の場合は、グループメンバーから医療連携に関連した質問を受け、そこから自組織の業務改善のヒントを得ることができました。
私はセカンドレベル修了により、専門職としての、生き方・働き方の選択肢を増やす事ができたと感じています。現在は転居に伴い、急性期病院に勤務しています。今後は在宅医療での看護 管理経験を活かしながら、環境変化に対応した新たなキャリアを構築したいと考えています。
認定看護管理者教育課程 サードレベルを受講して
NEW2024年度北里大学病院 熊坂 真由美
認定看護管理者教育課程サードレベル研修では、あるべき姿と現状とのギャップから真の問題を捉え、問題解決のプロセスを繰り返し学習しました。また、講義で得た知識を自分自身の言葉で表現する場面も多く、看護管理者として自分がどのような行動をとればいいのか、深めることができました。改めて、看護管理者の役割とは、医療や看護の質を保証し高めていくことであり、そのために組織変革を推進していくことの重要性を学ぶことができました。
国際医療福祉大学生涯学習センターでの研修は、オンラインによる授業がメインですが、グループワークを通じて、受講生同士のコミュニケーションが活性化し、活発なディスカッションが行われました。また、講師の先生方の手厚いサポートのもと、受講生の意見や思考を引き出しながら、適切なタイミングでアドバイスをしてくださるので学びが深まります。特に統合演習では、各グループ支援担当の先生が、熱心にご指導をしてくださいます。要因や現象を問題として捉え、真の問題にたどりつけず苦慮することもありましたが、先生方の熱意あるサポートのおかげで、組織改善に対する具体的な方策を示すことができました。統合演習は、研修生同士や講師との交流を深める良い機会となるだけでなく、受講生のモチベーションを維持することに大きく影響しました。
厚生労働省では新たな地域医療構想として、地域の患者・要介護者を支えられる医療提供体制の構築、限られたマンパワーにおける、より効率的な医療提供の実現などの検討をはじめました。こうした政策動向を見据え、看護管理者として質の高い医療・看護を提供するために何をすべきかを常に考え、行動していくことが求められます。この研修での学びを活かして、特定機能病院の使命を果たし、地域に根付いた高度な医療・看護を提供していくための管理実践に取り組んでいきたいと考えます。
私たちを導いてくださった講師の先生方、そして国際医療福祉大学生涯学習センターの先生方に心より感謝申し上げます。
2023年度中津胃腸病院 地域連携センター 神田 智恵子
私の住む大分県には、認定看護管理者教育課程サードレベル研修が受講できる教育機関がないため他県へ受講する必要があります。私は2023年度開催予定の教育機関の中から、仕事と研修を両立しながら学ぶことができる内容で「オンライン」受講が可能な国際医療福祉大学生涯学習センターの受講を選択しました。遠方からの参加で不安はありましたが、コロナ禍以降オンラインがスムーズにできる環境となっており、ディスカッションやグループ発表などの同期の皆さんとのコミュニケーションもスムーズで楽しく学ぶことができました。
その上、第一線で活躍されている素晴らしい講師の先生方から、オンラインで多くのことを学び、その中でも、今後のヘルスケアシステムの変化の中で求められる看護管理者の役割と2040年問題を見据え働く世代の人口減少による医療や看護に関わる状況を理解することができました。また、住んでいる地域の特徴と今後の自組織の役割を理解し、かかりつけ医療機関として在宅で生活する患者を支援し継続した看護ができる地域を巻き込んだ組織作りについて、演習につなげることができました。現在、訪問看護ステーションの開設や各部門看護管理者への教育を含めた看看連携体制の強化を実践し、住み慣れた家で患者が安心して療養できる体制作りを地域の多職種と一緒に取り組んでいます。
また印象に残っているのは、専任教員の先生方からの熱く思いのこもった支援です。管理者として様々な不安や悩みを抱えていましたが、オンラインからも伝わる先生方の優しさと叱咤激励のお陰で自分自身を見つめなおす機会となり、背中を押していただき踏ん張ることができました。
看護管理者として、「虫の目、鳥の目、魚の目」を持ち、地に足のついた現場感覚を忘れず、全体を俯瞰して見ること、時代の流れや社会の変化を敏感に感じ取り、進む道を決めていくことを実践していく決意です。今後も共に学んだ組織や地域を超えた仲間たちと「看護」を語り、励まし合うことのできる場所として大切にしていきたいと思います。